NO.41
新津保建秀 vol.6『風景を撮ること、人を撮ること』
INTERVIEW
2022/05/16 12:30
新津保建秀さんは、現在数あるメディアや媒体の多くで活躍する、第一線を駆け抜けるカメラマンである。国内外のさまざまな場所で写真撮影を手掛け、その対象はあらゆる著名人・文化人のポートレートから、巨大な展示物としての風景・建築写真などまで広範に渡る。
今回のインタビューでは、新津保さんの近年のプロジェクトを皮切りに、過去の原体験や人々との出逢い、ご自身の中で深めてきたテーマについて聞き、その創作に込められた思想や、写真表現の身体性・時代性・倫理の問題などまで広く深く語ってもらった。
彼はこれまでどんな経験をして、誰と出会い、そしていま何にレンズを向けるのか。
――ファインダーの奥にのぞく情熱の眼光に迫る。
崎谷 風景って結局、そういうことなんじゃないかと思うんですよ。本当は、外部化されえない経験がベースにあるというか、個人の見方に基づいて風景があると。
新津保 ああ、なるほど。修士のときの提出作品のタイトルは『往還の風景』という連作なんです。東京から息子が生まれる前に行った長野の山を再訪して写真を撮ったんだけど、そのとき、風景というのは、そこに行って捉えた一葉のイメージなのではなくて、どこかへ赴き、元の場所に戻ってくるまでの、心のなかにある前後の時間を含んだものであることが腑におちたのです。

《往還の風景》 (2016) ©新津保建秀
ライトジェットプリント 1200×1800
伊藤 新津保さんが撮られているものは、もちろん写真だから刹那的なものですが、時間的な奥行きがありますよね。写真はまさにその一瞬を切り取る芸術だと言われるけども、新津保さんの写真には、前後の時間を含めた、変化を感じさせるところがあるなと思います。
新津保 だといいですねえ。
伊藤 大学院の修了制作は、どのような形式でアウトプットされたんですか?
新津保 最終提出物は制作した作品と論文です。僕が提出した修了作品はドローイングと写真による連作です。在籍中の作品の講評は、先生方が一同に会するものがあって、これがかなり緊張感ありました。
伊藤 きつそうですね。
新津保 かなり。

博士修了展の展示(一部) ©新津保建秀
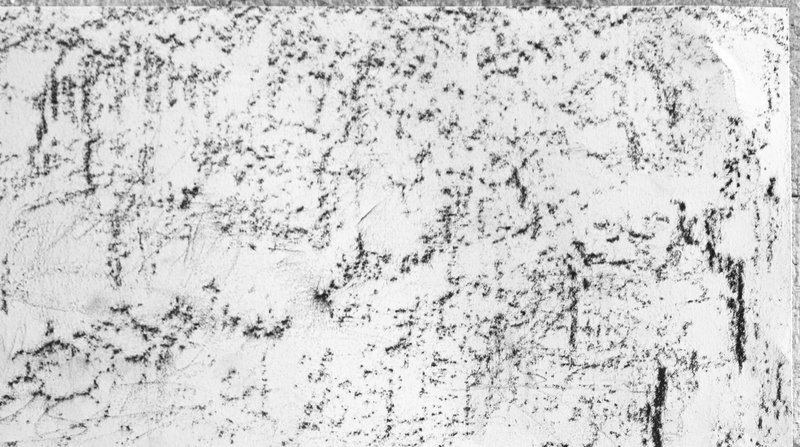
《Untitled》(2019) ©新津保建秀
ピグメントプリント 425×2376

《TimeScape》(2018) ©新津保建秀
映像(1min)から抜粋

《往還の風景》(2019) ©新津保建秀
ライトジェットプリント 1456×920
伊藤 メディアの違いは、すんなり問題なくいったんですか。写真と絵画ではだいぶ違うようにも思えますが。
新津保 自身の身体と扱う素材を介して、世界と関わっていくというところでは、絵も写真も通底する部分があるんですよ。それこそ、最近、20代のころに知り合った友人と3日連続で語りあう機会がありました。彫刻家の曽根裕さん(※)という人で、最初、藝大で建築を学んでから彫刻をはじめ、長年にわたって海外で活動されている方です。先日、彼が住んでいるベルギーから一時帰国しているとき空港から連絡をくれて久しぶりに会ったのです。そのとき、彼が彫刻の制作において、石という素材とイメージを扱う際の感覚に…
全文を表示するにはログインが必要です。