NO.38
新津保建秀 vol.3『空間の”奥”をとらえて』
INTERVIEW
2022/04/26 16:50
新津保建秀さんは、現在数あるメディアや媒体の多くで活躍する、第一線を駆け抜けるカメラマンである。国内外のさまざまな場所で写真撮影を手掛け、その対象はあらゆる著名人・文化人のポートレートから、巨大な展示物としての風景・建築写真などまで広範に渡る。
今回のインタビューでは、新津保さんの近年のプロジェクトを皮切りに、過去の原体験や人々との出逢い、ご自身の中で深めてきたテーマについて聞き、その創作に込められた思想や、写真表現の身体性・時代性・倫理の問題などまで広く深く語ってもらった。
彼はこれまでどんな経験をして、誰と出会い、そしていま何にレンズを向けるのか。
――ファインダーの奥にのぞく情熱の眼光に迫る。
崎谷 ヒルサイドテラスに住まれたのは何年からだったんですか?
新津保 2009年から2016年までです。北川さん(※)から、「朝倉さん(※)に紹介するからどうですか。中から撮ってみるとええよ」と言ってくれて。ちょうど息子が近所の猿楽小に通い、中学に入るまでの期間です。
※ 北川一成:株式会社GRAPH取締役社長
※ 朝倉健吾:朝倉不動産代表
崎谷 その辺の話は聞きたいですね。
新津保 住み始める前は、「たしかに仕事には便利かもしれないけど、もうすこし落ち着いた場所がいいのでは」と言っていたのですが、結論から言うと、住んでみたことで、実際に子育てをしながら長期にわたって撮る中で、建築の向こう側にある設計者の意図、その土地に漂う過去と現在の時間を写真の中のイメージに重ねてゆく感覚を獲得した気がします。今、言われるまで思わなかったけど。
崎谷 多分、住んだから言えることだと思いますよ。ただ第三者として撮って感じることと、自ら投資して住んで感じることは違う気がします。
新津保 あと、住んでみて、地域コミュニティーの中に深く入ってみたことで、設計者である槇さん(※)はこれをつくりたかったんだなというのは思いました。
※ 槙文彦:元東京大学教授, 槙総合計画事務所代

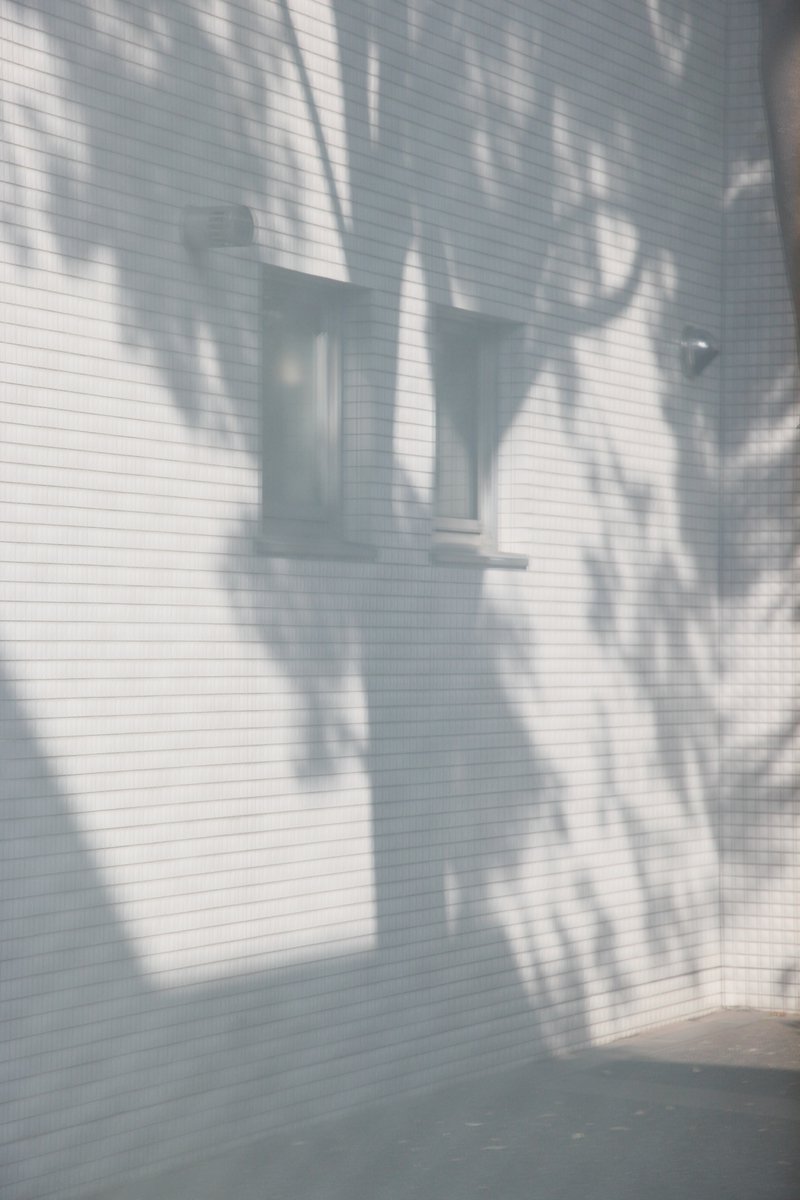



代官山ヒルサイドテラス ©新津保建秀
『HILLSIDE TERRACE 1969-2019 ―アーバンヴィレッジ代官山のすべて―』(監修:ヒルサイドテラス50周年実行委員会、現代企画 2019)より
崎谷 槇さんともよくご一緒されました?
新津保 建築空間を撮影するときは朝倉健吾さんとご一緒することが多かったです。槙さんと御一緒したのは、ポートレートの撮影が多かったですね。

建築家の槙文彦さん ©新津保建秀
『HILLSIDE TERRACE 1969-2019 ―アーバンヴィレッジ代官山のすべて―』(監修:ヒルサイドテラス50周年実行委員会、現代企画 2019)より
新津保 一番、最近だとパスポート更新用の写真です。撮影のあと、「10年後(の更新)も」とにっこり仰ったとき、この方はずっと現役なのだ、それがすごいなと思いました。
伊藤 お元気ですね。
新津保 そうなんですよ。何故そんなにお元気であるかを聞いたら、「私はどこに行くのでも歩くのです」と仰っていました。ご自宅から品川の駅まで歩いて、山手線で恵比寿に行って、恵比寿から今度は駒沢通りをず…
全文を表示するにはログインが必要です。