NO.64
原広司 vol.0 『序章:世界の実存と虚構性』
INTERVIEW
2023/02/24 01:30
20世紀を代表する世界的な建築家・原広司さん。
その建築作品は国内外を問わず高く評価されており、代表作はJR京都駅、大阪梅田スカイビル、札幌ドームなど、誰もが一度は見聞きし、訪れているだろう建物である。しかし、その作品の規模・形態・機能の多様性は凄まじく、おそらく日本でもっとも様々なタイプの施設を設計した建築家でもある。原さんの建築はグローバルでもあり、ローカルでもあるという、二つの事象が同時に観測される。そして、その空間は、時間や環境の変化に対して、実に多様に展開することも特徴である。
また、その一方で、原さんは言葉の人でもある。1960年代からこれまでに様々な著作・論文を通じて、建築界に大きな影響を与えてきた。その言説は、数学や物理学、芸術と音楽、思想哲学、歴史、宗教などの垣根を易々と超え、かつ独自の視点で結びついている。
今回のインタビューでは、そんな原さんがどこで生まれ、何を体験し、何故そのようになったのか、という素朴な疑問を、我々の問題意識と結びつけながら質問した。また、戦後の20世紀という濃密な時代を、建築家・思想家として、どのように捉え、駆け抜けたのかについても語ってくれた。
屈指の名インタビューとなったことを確信している。
戦災と飢餓を生き抜き、世界中を旅してきた巨人が、いま自身の人生について口を開いてくれた。
我々もまた、神に代わる、武力に代わる、新たなフィクショナリティーを求めて旅に出よう。
2022年某日。
東京は渋谷の繁華街から少し外れたところに位置する原広司先生の事務所にて、直接お会いすることができた。なにぶんコロナになってから2年が経っても対面でインタビューをさせてもらえるチャンスというのは貴重で、その相手が齢85を数える原先生ともなれば、この機会が計り知れなく恵まれたものであるのは言うまでもない。
当の原先生は、あっけらかんとしていた。
我々がインターフォンを押し、玄関でおずおずと靴を脱いで、スタッフさんに案内してもらうと、
「まあ、何事も焦ったりしなくて良いから」
と、ゆったり椅子に座り、煙草をくゆらせていた。
「今日はよろしくお願いします。」
あらためて挨拶をし、インタビューの機会をもらえたことに感謝を伝えた。事前に送っていた質問状の印刷したものを渡し、まごまごとカメラや録音機をセッティングする。その間、コーヒーを準備して戻ってきた原先生は、机の上に置かれた質問状に一瞥すると、あらためて椅子に腰かけてポツポツと話し始めた。
「いま吉見(※1:吉見俊哉)と対談して、本を書いているんだけどさ。吉見っていうのは僕の研究室にいたんだよ。その後、見田(※2:見田宗介)研究室に行くんだけどさ。たしか、隈(※3:隈研吾)とか小嶋(※4:小嶋一浩)がいた頃だよ。それで、その彼がね、あなたが送ってくれた質問とほとんど同じことを考えているんだね。だから、そのことについてずっと、この半年くらい考えていてね。」
「え、そうなんですか」と思わず声を漏らした。機材を調整していた手が止まる。
「本当は吉見の本のために考えていたことなんだけど、だからと言って、隠すってのもさ。」
原先生は笑って、そう付け加えた。
我々の用意していた質問を箇条書きにすれば、下記の通りである。
① いま建築に何ができるのか
② 原先生の建築的命題とは何だったのか
③ 原先生の原体験・原風景について
④ 建築家を目指したきっかけについて
⑤ 世界中を旅して見てきたことについて
⑥ これからのことについて
⑦ 肉体的・精神的に還る場所について
これらの質問は、具体的に我々が抱えている悩みと、現代社会の状況と、原先生の人生や活動に対する興味を、土景というメディアを介して切り取り、端的にまとめたものである。
「具体的に、どのあたりが重なっているんでしょうか?」
「だいたい全部重なってるんですよ。」
「全部ですか?」
あの吉見さんを相手に、まさかそんなわけはないだろうと驚き、俄かに汗ばんだ。
「だけど、それは喋る度に違う内容になるだろうし、いいんだよ。とにかく、いろいろなことを最後に整理しようとしてきていて、少しずつまとまってきたんですよ。つまり、私は何をどういう風に語れば良いのか、その語り方についてね。だけど、それは非常に多岐に渡っているので、こういうところで話すのが良いのかどうか…」
原先生は、静かに頬に手を当てた。
「インタビューでは難しいですか?」
「つまり、説明し切れないじゃない。いろいろなことを分かりやすく単純化して言うことが必要と思うんだけど、でも物事にはすごくディテールに関わるようなことを言わないと伝わらない、そういうこともあるわけだから。」
まさに、と我々も頷いた。原先生は一呼吸おいてから、
「とはいえ、まあ、そう上手くいかないこともある。それを気にしすぎて喋っても仕方ないからね。なにしろ本質的な問題というのは、誰が聞いても分かるような基本的なことでもあるし、けれど答えが単純に決まってるでもなし。聞かれる度に違うんだろうし。」
と、少し開き直ったように、そう言ってくれた。
インタビューのような会話形式で出てくる情報というのは、そのままテキストに起こしていくと分かるが、実はそのバランスが結構めちゃくちゃである。会話はその場限りのセッションであるから、膨大な思考の連鎖からどんな情報がどういうかたちで飛び出してくるかをコントロールし、図ることはできない。
原先生はそのことをよく知っている風であった。そして、今まさに語ろうとしている内容に比して、時間が足りないこともきっと分かっている。だから、どういうふうに話をしようかと精査し、言葉を探しているように見受けられた。
結論から言えば、当初2時間で予定されていたインタビューは、最終的に4時間を超えた。そして、今回の記事は、冒頭の約1時間分を序章として書き下ろしたものである。なぜこんな体裁をとったかといえば、つまりその1時間は非常に難解だったからに他ならない。
原先生の中には、絶えず揺らぎが存在していた。論理的に結論を収束しようとしながら、“さにあらず”を繰り返す。まるで着地しようとしながら再び舞い上がるパラグライダーのようである。AはBであるがBでない。それなら、B‘であるかもしれないが、そうでもない。では、B”かもしれないが……と延々と続くのだ。それは、物事を精確に語ろうとするときの言葉や論理の不十分を自覚し、それを満たしていこうとするも満ちることがない、“あらずあらず”の態度として現れてくる。
また、こうした事態を生む背景には、公理の立て方そのものに間違いがあるのかもしれないとも指摘する。つまり、「AはBであるか否か」という問いを立てたその時点で、あるいは何かの事物を「A」「B」と断定したその時点で、すでにどこか違えているかもしれないというわけだ。原先生との会話は、こうしたディテールの蓄積として立ち上がっていく。
我々の方から最初に切り出した質問はこうであった。
「まずは、<いま建築になにが可能か?>という質問についてお聞きしたいです。というのも、僕らは建築や土木構築物をデザインする人間ですから、日々の設計を通じて、なにかをつくり、未来に残すということを考えています。しかし、現代社会を見渡したときに、自分達の使命となるような命題がもちづらいのです。つまり、何を目指して設計するのか。眼前の具体的な問題は山積みだと思いますが、より長期的な視点で考えたとき、何を根拠に設計をするべきか。そうしたことが不確かで、問いが上手く立てられていないのです。」
筆者がそこまで話したところで、原先生は、うんうんと頷いた。
「それは今度の本にも書こうと思っていることだけど」
と断りながら、原先生は続けた。
「重要なことはフィクショナリティーなんだよ。つまり、虚構性。」
心外な言葉が急に飛び出してきた。なぜなら、建築設計は現実を直視し、その問題を解決することに重きを置くことの多い分野だからである。
しかし、原先生は次のように言い切るのであった。これまでさまざまな建築設計や都市計画に関わってきたが、けっきょく建築はインフラストラクチャ―に触らせてもらえないのだから“比喩的に現れる”ほかないのだ、と。だからこそ、それらはフィクションを必要とするのだという。
そして、そのことを考えるために重要な参照点だとして、2人の文学者の名前を挙げた。一人はH.D.ソロー(※5)、そしてもう一人はT.S.エリオット(※6)である。
H.D.ソローは19世紀前半の1830年頃から台頭してきたアメリカ・ルネサンスと呼ばれる時代の作家である。時はまさに近代化の黎明期であり、南北戦争の前後にあたる。18世紀末に国家としての独立を果たしたアメリカは、産業革命によって一気に発展が進み、文化においても、そのルーツたるイギリスの影響を脱して独自の芸術性を拓こうとしていた。同時代にはエマーソン(※7)、ホイットマン(※8)、ディキンソン(※9)、メルヴィル(※10)といったアメリカ古典文学の歴々が名を連ねる。
この時代における重要な思想の一つは、エマーソンの唱えた“超絶主義(transcendentalism)”である。それはありていに言えば、“神ではなく人間に価値の重きをおく”一種のアメリカ的プラグマティズムであった。その背景にはヨーロッパという故郷を脱して広大なアメリカ大陸を横断する自由闊達な開拓精神と、かつてのカソリック的宗教制度から逸脱してきたプロテスタンティズムの精神、ピルグリム・ファーザーズの魂が同居していたと思しい。当代のアメリカ文学は少なからずこの”超絶主義“に対する応答であった側面が見受けられる。
ソローは、エマーソンに対して一定の共鳴をしていた。その著書『ウォールデン:森の生活』(1854)では、ソロー自身が自然世界の中で自己を追求する“森の生活”をし、自然の野生との一体感を得られることに価値を見出していたことが記述されている。

ヘンリー・デヴィッド・ソロー Henry David Thoreau(1817-1862)
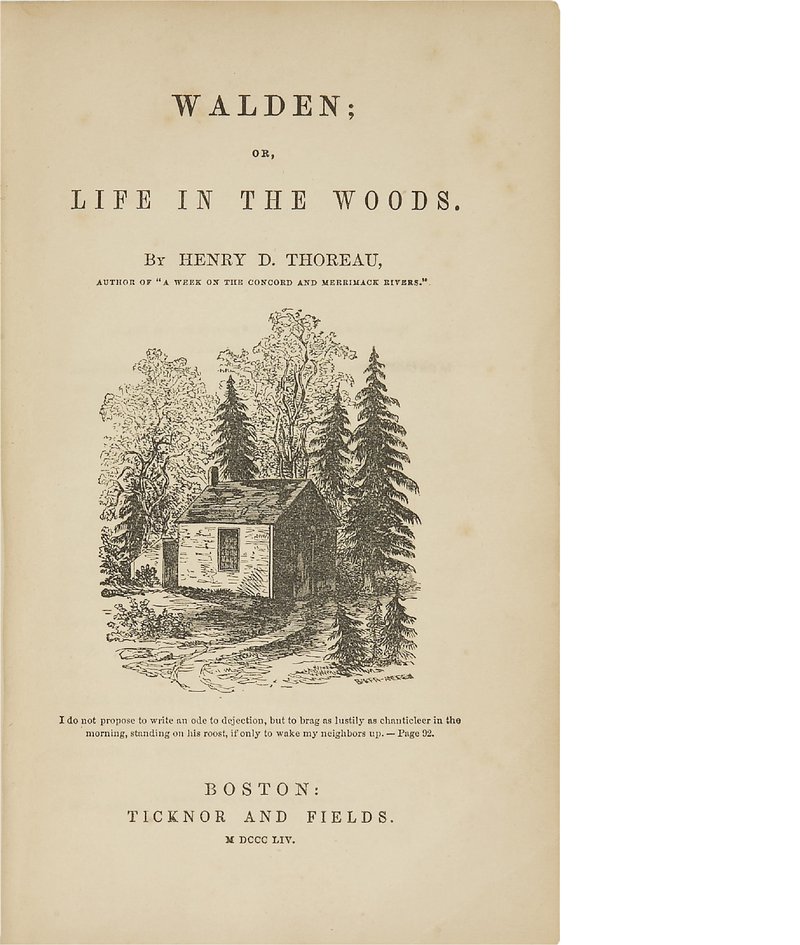
H.D.ソロー『ウォールデン 森の生活(原題:Walden; or, Life in the woods)』(1854)
そして、原先生は、この“森の生活”に対する共感が止まないのだという。それは人間を自然世界の中の実存として位置づける、きわめてプラグマティックな態度なのである。そこには途方もなくリアルな自然の世界が現前している。
そして、このようにも述べる。
「たとえば鴨長明(※11)。あれは日本建築史上、最大の発明家だと思うね。」
この発言は、鴨長明のつくった方丈庵をさしている。森の中の庵であるが、不必要なものを削ぎ落していった結果、庵はどんどん小さくなり、最終的には内と外が反転した――そういうパラダイムシフトを起こしたのである。建築をつくるということは、ともすれば、その内側の欲求を満たしていくことのように考えられているが、実はそれだけではない。むしろ外側との接点をどのように持つかということが、際立って重要である。原先生は、鴨長明がいたった発想こそ、巨大な寺院や城をつくるよりも遥かに偉大な所業であり、世界的にも類まれに優れたものだと評価する。
原先生は、このソローや鴨長明に通ずる“森に入って建ててみよう”という精神に強く共鳴し、自邸において実践した。
<Reflection House=反射性住居>と呼ばれるシリーズに位置づけられるこの自邸は、神奈川県町田市の豊かな原生林の残る傾斜地に建てられている。


原先生の自邸内観 ©山田脩二
「1973年に建てた住宅なんだけど、最初から土地を少しだけ広くして、森が残せるようにはしたんだ。今どうなっているかというと、僕の家の周りのところだけ、その原生林が孤立して残っている。そこは白樫や欅やその他の樹種もたくさんあるところなんだ。けど、周りは全部切られてしまって。僕も残そうと相当あれやこれや言って努力したんだけどダメだったね。でも、一昨年に狸が2匹やってきて、昨年に4匹の子供を産んだんだよ。」
「それは凄いですね。今でも町田に狸の出るところが…」
「だから、それは最大の名誉だと思っている。」
原先生は力強く答えた。
「建てた当時は森の中に野兎がいたんだよ。ぴょんぴょんと飛んでいくの。それに、フクロウもいたし。」
原先生の自邸は、森を残すことに成功したのであろうか。
「ソローの本を読んでるとね、根本的なところを言うとね、この人は非常に優れたランドスケープ・アーキテクトなんですよ。専門家だということじゃなしに。専門家は、環境も建築も都市の話もするし、それはそれで良いんだけどね。それに、当時のアメリカと現代の日本を比べても、人口密度やら環境やら、差異の方が圧倒的に多いから比較なんてするつもりもないんだけれど。なにしろ基本的なことは、この人は、いい人なんですよ。いい建築家なんです。」
よき人であることと、よき建築家であることは原先生の中で密接に繋がっている。これは倫理観や親切心というだけでなく、根本的な人としての生き方――つまり、どのように考え、何を実行したのかを含んでいる。原先生がソローを信用しようと最も強く思うことになった、下記のような逸話がある。
「ウォールデンの森に住んでいる住人たちは、ウォールデン湖が世界の反対側に通じているということを、かなり信じていたらしいんだ。当然そんなわけはないんだけど(笑)、それについてソローはね、そういうこともあって良いんじゃないかって、批評として言っているんだね。私が建築で有孔体理論というものを考えたときに、それは最初なにもないボールのようなものがあって、そこに穴をあけることで内と外とが繋がるという話なんだけど、ウォールデン湖のそれはね、世界の向こう側まで繋がっているというのはね、なかなか良いじゃないかと。間違っているんだけど、とても美しいっていうのかな。それで、私は日本の対蹠点(たいしょてん, たいせきてん)であるモンテ・ヴィデオ沖まで行ってね、それ以来ずっと南米と関わるようになるんです。」
ソローはウォールデンの住人の美しいフィクションを否定しなかった。むしろ、同じ森の中に住み続けたことによって、それを肯定さえしたかもしれない。その向き合い方は、投げやりではなく、真剣そのものと言ってよい。
「なにか実験してみようという人生がすごく重要で、共感できるわけです。鴨長明も実験したわけですよ。住居だって少なからず二度、三度建てて、その過程で、縮小していくと内外の反転が起こった。そういうことを知るために、山の中に入っていった。つまり、実験していた。人生は実験なんだよ。そういうところは似てる人がいるわけだよ。」
原先生が世界中の都市村落の構造を解き明かすための旅に出た背景には、ソローのような体験主義と実証精神が横たわっていたのである。
さて、もう一人の人物であるT.S.エリオットは、20世紀前半の詩人である。生まれは19世紀末だが、その代表作の一つとして知られる『荒地』は第一次世界大戦の後である1922年に初稿版が発刊されている。エリオットの作品は一般的にブリコラージュ、すなわちイメージの結合として語られることが多い。

トーマス・スターンズ・エリオット Thomas Stearns Eliot(1888-1965)
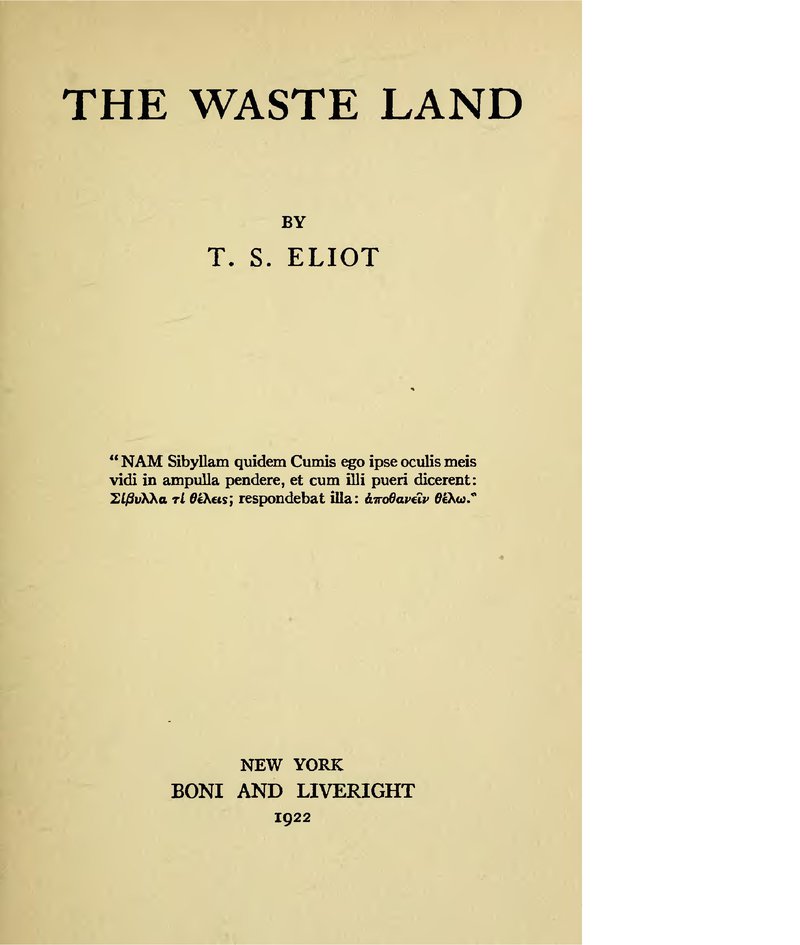
T.S.エリオット『荒地(原題:The Waste Land)』(1922)
「だけど、エリオットを解釈しようとすると、ちょっと嫌らしいところがあるというかさ。彼はイギリス国教のキリスト教信者なんだけど、東洋をいろいろ見たんだ。インドの話とかもたくさん出てくるんだね。ただ、その後の作品でけっきょく彼は、自分はやはりキリスト教徒だとあらためて書く。だけど、とにかく、ものすごい量の知識を引用するんだ。そして、さらに、その引用の歴史もすべてちゃんと自分で解説しているのがすごい。後に、構造主義者たちは彼をブリコルールと呼んだ。その手法は先に美学的方法としてマックス・エルンスト(※12)がつくっていたんだけど。」
原先生いわく、エリオットは予言者である。エリオット以降の世界、20世紀は近代の頂点を迎えてコラージュの世界となったのだ。たとえば、建築も、都市も、もはや事前に部品はすべて揃っていて、設計者はそれらを集めてつくることしかしなくなった。
「そのこと自体はよくないというか、ブリコラージュの世界っていうのは、基本的にはよくないと思う。ただ、エリオットは世界がそうなることを予言していたんだね。僕が学生だった頃は、もうT.S.エリオットは絶対に避けられない存在だったように思う。それくらい世界はエリオット的だった。だから、みんな当然知っているんだけど。」
原先生は、1925年という年を一つの転換点として捉えているという。それはハイゼンベルグ(※13)の運動方程式が示された年であり、翌年にはシュレーディンガー(※14)の方程式も提示されたことで量子力学の嚆矢が放たれたときである。すなわち、1925年とは、サイエンスによって世界の認識方法に大きく革命がおこされた年である。これは現代から100年ほど遡った出来事にあたり、ちょうどエリオットが『荒地』を著した時期と符合する。つまり、一方では近代が頂点を迎えた瞬間であり、もう一方では人類にとって決定的に世界の見方が変わった瞬間であった。原先生は自らをこの転換点以降の世界の人間だと位置づけている。
そのエリオットが没したのは1965年である。そして、彼の墓碑銘には“わたしの終わりには、始まりがある”(原文: In my end is my beginning )というようなことが書かれている。
「要するに、彼は一神教じゃないんだと思うね。生と死に関する時間概念が、少なくともキリスト教的でないというかさ。」
何故、このような話が出るのか?
それは、“神”の問題を考える上で重要だからである。つまり、それはフィクションの問題を考える上で重要なのだ。
エリオットの時代から、さらに100年を遡ると1825年となる。これはエマーソンが“超絶主義”を唱え始めたときであった。そしてその後、それに共鳴したソローが“森の生活”を始めることになる。この時期のアメリカはヨーロッパ的伝統から離脱するための葛藤をし、新たなプラグマティズムが思想・芸術として胎動を始めていた。やがて、それは武力と資本によって形姿を変えて世界を席巻することになるが、その前夜における大きな思想転換が、まさにこのときにあったのだ。
1825年と1925年。
このように区切って見ると、それは“神”をどう考えるかという点において大きな変化を象徴している年代である。
原先生はソローとエリオットの共通点が、バガヴァット・ギーター(原題: Bhagavad Gita)にあるとする。それはバラモン教およびヒンドゥー教の最高聖典であるが、紀元前を何千年も遡る古代の宇宙創成期であり、至高の神・クリシュナにまつわる話である。

クリシュナとアルジュナ王子の対話を描いたとされる絵画(インド, 1830)
The British Museum公式HPより
「アメリカの学者たちがどれくらい分かっているか興味があるけどね、2人ともバガヴァット・ギーターの信者なんだよ。キリスト教徒だってのに変な話だと思うんだけど(笑)。キリスト教では神が最初に光あれと言って宇宙をつくったと、世界をそういう風に信じようとしているわけだけど、どう考えてもそれでは頼りなかったんだと思うんだよね。」
彼らにとって、一神教的な世界解釈だけでは、貧弱で信じるに足りなかった。そうであるなら、“神はいない”とするか、あるいは“神は多数いても良い”とするか、どちらにせよ別の説明が必要になったはずである。そのとき、世界の構造を別の見方で捉えてみようという活動があらわれてきた。
これは、言い換えれば、リアリティーを捉えるための眼差し=フィクションが進化する瞬間である。
ソローがリアリティを追求して森の生活に入っていった結果、ウォールデンに暮らしてきた人々のフィクションに共感を覚えたように。あるいはエリオットが近代都市という、神を離れて蠢く謎の運動体に分け入った結果、世界の解体と再構成を生み出し続けるコラージュの仕掛けを見たように。
さて、次は2025年を迎えようとしている。
我々はどのようなフィクションをつくり、拠り所とすることができるのだろうか。
※1 吉見俊哉:1957-, 社会学, 東京大学教授
※2 見田宗介:1937-2022, 社会学, 東京大学名誉教授
※3 隈研吾:1954-, 建築家, 東京大学名誉教授, 隈研吾建築都市設計事務所主宰
※4 小嶋一浩:1958-2016, 建築家, 元横浜国立大学大学院Y-GSA教授, シーラカンス・アンド・アソシエイツ共同主宰
※5 ヘンリー・デヴィッド・ソロー:1817-1862, アメリカ, 作家, 詩人, 思想家, 博物学者
※6 トーマス・スターンズ・エリオット:1888-1965, イギリス(アメリカ生), 詩人, 文芸批評家
※7 ラルフ・ウォルド―・エマーソン:1803-1888, アメリカ, 詩人, 作家, 思想家, 哲学家
※8 ウォルト・ホイットマン:1819-1892, アメリカ, 詩人, 随筆家, ジャーナリスト
※9 エミリー・エリザベス・ディキンソン:1830-1886, アメリカ, 詩人
※10 ハーマン・メルヴィル:1819-1891, アメリカ, 作家, 小説家
※11 鴨長明:1155-1216, 歌人, 文人
※12 マックス・エルンスト:1891-1976, ドイツ, 画家, 彫刻家
※13 ヴェルナー・カール・ハイゼンベルグ:1901-1976, ドイツ, 理論物理学者
※14 エルヴィン・R・J・A・シュレーディンガー:1887-1961, オーストリア, 理論物理学者
(文責:土景編集部 伊藤遼太)
次編からインタビュー本編へ
<次編: 原広司 vol.1 『戦災、飢餓、貧困の中で、神様はいなかった』>